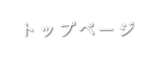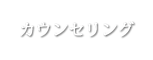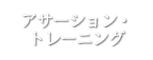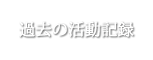PAST ACTIVITY
- 最新号 号外 2009年9月発行
- No35 2009年9月発行
- No.34 2008年9月発行
- No.33 2007年10月発行
- No.32 2007年6月発行
- No.31 2007年1月発行
- No.30 2006年10月発行
- No.29 2006年6月発行
- No.28 2006年2月発行
- No.27 2005年11月発行
- No.26 2005年8月発行
- No.25 2005年5月発行
- No.24 2005年1月発行
- No.23 2004年9月発行
- No.22 2004年2月発行
- No.21 2003年10月発行
- No.20 2003年8月発行
- No.19 2003年5月発行
- No.18 2003年1月発行

-
号外の発行にあたって
Sさんご夫妻はある出来事をキッカケとして、
とてもしんどい体験をされました。
それは一見、私たちのふだんの生活とは
まったく関係ないことのように見受けられます。
でも、ちょっと振り返ってみると、ここでの問題は形を変えて、
私たちの周りでもいろいろな場面で見ることができるようにも思います。
見えにくい性差別に対して声を上げていくことの大変さ。
しかしだからこそ、声を上げると見えてくる問題の本質。
ご夫妻それぞれの視点で書いていただきました。■私は声を上げた K.S
私は昭和30年代の生まれである。私の母は大正生まれ。母はある地方の片田舎の素封家の家に生まれ、昔気質の頑固親父と従順な母との間に生まれた。私は幼い頃から、「学校の先生は女の人が多いけど、男の先生の方がいいわね」、「お医者は男の先生の方が信頼できるね」と幾たびとなく、母から聞かされていた。そして、私が「不動産鑑定士」という資格を取って独立した時、母は私にこう言った。「女性は軽く見られるから、誰もあなたのいうことなんか聞かないわよ」と、私を産んでくれた母親とは思えないきつい餞(はなむけ)の言葉を私へ吐いたのである。
仕事を始めてからは、女性というだけで名刺交換の対象とは見てもらえなかった。面と向かって宴会の席で「女性はお茶出しや酒のお酌は、言われなくても真っ先にするものだ」と年配の男性から言われたり、「大きな仕事の責任者は女性には無理だ」と言われた時もあった。また、ある審査会の席上、役所の職員の前で「勉強不足だ」とことさら悪意を含んだ表現にさらされた時もあった。そんなある日、私の所属する団体主催の公式の会議中に、強い精神的なショックを受ける事件が起こった。
「うるさい。だまれ!やりたいなら代わりにやれよ。勝手にやればいいじゃないか!」と突然大声を上げられた時、私は呆然とし、何が何だかわからなくなっていた。3年に1度行われる大事な会議の席上、机に広げた図面を見ながらの議論に加わろうと、机の前に一歩踏み出した時だった。一言も言葉を発していないにもかかわらず、暴力的な言葉を投げつけられたのだ。周囲の私に対する好奇や揶揄するような視線も感じた。わき上がった感情は大きかった。「ふざけるんじゃないわよ。どこまで私を虐げれば気が済むの」そして、私の中の自分が「何を我慢しているの。何を守ろうとしているの。これでいいの?」と責め立てた。
真っ赤に焼けた金づちのような鈍器で、思いっきりなぐられたような感覚であった。 私の目に入る周囲の景色は、その時から動きを止めた。「もう、目をつぶるわけにはいかない」私は呆然としながら、帰路の運転中、「暴力」という2文字がぐるぐる頭の中を駆けめぐっていた。これは、女性である私へ向かって、意識的に男女差別を表した、言葉による暴力だと思った。
これから、どういう手段で立ち向かうべきか思いをめぐらしていた。ハンドルを持つ手が汗ばんでいた。私は以前より、所属団体の総会等の会議に出席した後、ひどい疲労感と倦怠感を覚えていたことを思い出していた。そうなのだ。ずっと前から、私に対して向けられていた視線や態度の意味するもの。それは「なんで女のおまえがおれ達と同じ資格を取って仕事しているんだ。家で子供でも産んでジッとしていればいいじゃないか。」というメッセ-ジであり、暗黙のうちに行われている抑圧であるとはっきりと自覚できたのは、皮肉にもこの時であった。男と女、強いものと弱いものの構図。私の体の中から、私自身を突き上げるエネルギ-を抑えることはできなかった。
私は、専門職業家として恥じることのないよう、できるだけの努力と研さんを積み重ねてきたつもりである。生来、何事にもがむしゃらに取り組む性格であったことも手伝って仕事は順調であった。「女性」という性別だけで異質なものと扱う男性達(同じ資格を有する人達)にとって、私という存在は紛れもなく否定したいものであったろう。私は、所属する団体ではいつもカヤの外であった。それは、男性にとっては本能的な行動なのかもしれない。だから、本当に質が悪いのだ。「怒り」という感情は、私を臨戦態勢へと押し上げた。「絶対、後にはひけない」
たぶん、どんな職種でも、女性が働き始めた時、一番最初に感じることがあると思う。それは、「男性と女性のスタ-トライン」が違うということだろう。私はそれを感じつつ、直視せずに、ただひたすら職務を全うしてきた。もちろん中には少数ではあるが、私の働きを認めてくれる人もいた。だから、ここまで仕事を継続してこられたのだと思っている。
しかし、「口封じ」という男性側の力の論理を駆使して、公衆の面前で人権を侵害されたのだ。許せない。もう自分自身を落ち着かせる方法は持っていなかった。
所属団体へ私の代理人を立てて申し入れをしたが、団体からの誠意を表す態度は一切見られず、ほとんど返答のない状態にあり、また、私の所属する団体の許認可権者である県へ、このような差別を容認している団体に助言等をしてほしい旨の要望書を提出しても、私の方には何の連絡もなく、私の知らないところで偏った調査しか行わず、「何の問題もない」とする見解を言い放つ地方公共団体。これが、現在の日本の社会の現実なのかと愕然とした。
私が主張していることは、間違っているのだろうか。いや、正しいことを言っているはずだ。私は歯がゆかった。「男女差別」をまともに扱ってくれる機関は、私の近くにはないらしい。息苦しい。人間として、個人として自由に生きることがこんなに難しいこととは思わなかった。
「差別」は、空気のようなものだと思う。音もしなければ、姿、形があるわけではない。だから、手ごわいのである。でも、誰もが大なり小なり直面するものでもある。そして、今までズーッと私は男女差別を受けてきたのだ、とはっきり自覚できた瞬間、私は弾けた。「なんのとりえもなく力もない一個人であるけれど、声を上げよう。黙っていることはもうやめよう。このことを一人でも多くの人に知ってもらい、考えてもらおう」
また、これは、ちょっとした偶然で、「巡り廻って今度はあなたの順番よ」と、差別と戦ってきた先人達からバトンを渡されたような気もする。そして、このバトンは必ず私から将来誰かの手へ渡さなければならないもの。そのバトンを、今、私は手にしている。そう感ぜずにはいられなかった。
私は、どんな小さなことでも、女性も男性も関係なく、「それっておかしいよね。ジェンダー(バイアス)じゃないの?差別じゃないの?」と率直に声に出せる社会になるよう願わずにはいられない。従順だった女性達が言語を獲得し、男性と対等に自由闊達に議論し、主張できる環境は、社会全般にはびこっている現代の停滞感や閉塞感を払拭する最大の武器になるものと信じている。 私は私らしく、何者にも縛られず、何色にも染まらず、自由に生き生きと暮らしたい。それが、私のたった一つの願いである。